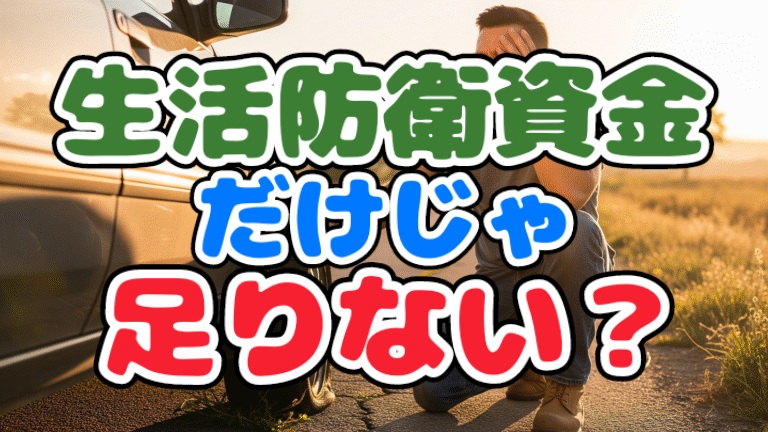投資や資産形成を始める時、まず意識しなければいけないのが「生活防衛資金」です。これは万一の収入減少や失業に備えて、生活費の半年〜1年分を現金で確保しておくものです。
しかし実際に家計管理や投資を続けていくと、生活防衛資金とは別に用意すべき現金=予備費の存在が非常に重要であることに気づきます。
この記事では生活防衛資金と予備費の違い、なぜ予備費が必要なのか、いくらくらいをどのように備えるべきかを投資家目線で詳しく解説します。

生活防衛資金と予備費の違い
まずは言葉の整理から。
- 生活防衛資金:失業や病気などで収入が途絶えた場合に備える生活費(6か月〜1年分が目安)
- 予備費:日常生活で突発的に発生する支出に対応するための資金
つまり生活防衛資金は「収入が途絶えたときの命綱」、予備費は「突発的な出費に備えるクッション」と言えます。
投資を始める前に生活防衛資金を確保しておくのは鉄則ですが、それだけでは安心できません。
実際に生活していると、予定外の支出は必ず発生するからです。
予備費が必要になる場面
では、どんなときに予備費が役立つのでしょうか。具体例を挙げます。
- 家電の故障・買い替え
冷蔵庫やエアコンが急に壊れると、数万円〜十数万円の出費が必要。 - 住宅や車の修繕費
持ち家なら水回りや屋根の修理、賃貸でも更新料や退去費用が発生。車も車検やタイヤ交換など不定期にまとまった支出があります。 - 冠婚葬祭費用
ご祝儀や香典、交通費など、急に必要になることも多い。 - 子どもの教育関連の臨時費用
部活動の遠征費、入学時の制服代など、計画外の支出が発生することも。
このような出費は「生活防衛資金」から崩すべきではありません。なぜなら生活防衛資金は“非常事態のための資金”だからです。日常生活での突発支出は別枠で備えておく必要があります。

予備費はいくら用意すべきか?
では、予備費はどれくらい必要なのでしょうか。一般的な目安としては生活費の1〜3か月分程度です。
例えば、月の生活費が25万円の家庭であれば、25万〜75万円を「予備費」として現金で確保するのが安心です。
- 単身者:生活費1か月分程度(10〜20万円目安)
- 夫婦二人暮らし:生活費2か月分程度(40〜50万円目安)
- 子育て世帯:生活費3か月分程度(70〜100万円目安)
大切なのは、生活防衛資金を切り崩さずに「予備費」で日常的な突発支出を吸収できることです。
予備費をどこに置くべきか?
予備費の性質上、すぐに引き出せる形で持っておくことが重要です。代表的な置き場所は以下の通り。
- 普通預金口座
最もシンプル。すぐに使える。 - 貯蓄用サブ口座
生活費口座とは分けておくと管理しやすい。 - 現金(手元保管)
災害時の停電などに備え、数万円を現金で持っておくのも大切。
投資商品に回すのはNGです。予備費は「安全・流動性」が最優先であり、リスク資産にしてはいけません。

投資家にとっての予備費の重要性
投資をしている人にとって、予備費を持つことは特に重要です。理由はシンプルで、突発的な出費に備える資金がなければ、投資資産を不本意に売却しなければならなくなるからです。
例えば株価が大きく下落しているときに、車の修理代が必要になったとします。予備費がなければ、株を安値で売却して現金を作らなければならないかもしれません。これは大きな機会損失になります。
つまり、予備費は「投資資産を守るための防波堤」として機能します。
生活防衛資金+予備費で安心の二重構え
ここまでを整理すると、投資を始める前に用意すべき現金は以下のようになります。
- 生活防衛資金:生活費6か月〜1年分
- 予備費:生活費1〜3か月分
これを二重構えで確保しておけば、どんな不測の事態にも対応可能です。
生活防衛資金は「収入がなくなったときの命綱」、予備費は「日常の突発支出のバッファ」と役割を分けて持つのが理想です。
まとめ:投資を始める前に予備費を確保しよう
- 生活防衛資金は「収入が途絶えたときのため」
- 予備費は「日常の突発支出のため」
- 予備費の目安は生活費1〜3か月分
- 置き場所は普通預金やサブ口座が基本
- 投資家にとって予備費は「資産を守るための防波堤」
投資のリターンを最大化するには、下落相場で資産を売らないことが重要。そのために、予備費をしっかり確保しておくことは欠かせません。
「生活防衛資金+予備費」という二重構えを作ることで、家計も投資も安定し、安心して長期的な資産形成に取り組むことができるでしょう。