「毎月の保険料が家計を圧迫している…」
そんな悩みを抱えていませんか?
生命保険や医療保険、がん保険などの民間保険は、安心のために加入するものです。
ですが、公的保険制度と重複して保障を受けているケースも多く、見直すことで月々数千円〜数万円の節約が可能です。
この記事では、
- 公的保険と民間保険の役割の違い
- 民間保険の保険料を抑える具体的な方法
- 見直し時の注意点
を初心者にも分かりやすく解説します。

公的保険と民間保険の違いを理解しよう
公的保険とは?
日本では社会保険制度が整備されており、病気やケガ、死亡、老後などのリスクに備えるための公的保険が用意されています。
主なものは以下の通り。
- 健康保険(国民健康保険・社会保険)
医療費の自己負担が原則3割になる制度。高額療養費制度で医療費の上限も設けられています。 - 国民年金・厚生年金
老後の生活保障や障害年金、遺族年金として機能。 - 雇用保険・労災保険
失業時や労災事故の際に給付が受けられる。
民間保険の役割
公的保険でカバーできない部分(先進医療費用、入院時の差額ベッド代、死亡時の家族の生活費補填など)を補完するのが民間保険です。
民間保険の保険料が高くなる理由
- 公的保険との重複保障がある
- 過剰な特約を付けている
- 加入時期が古く、最新の安価な商品に切り替えていない
- 年齢や持病により保険料が上がっている
こうした理由を見直せば、大幅な保険料削減が可能です。

民間保険の保険料を抑える具体的な方法
公的保険でカバーできる部分を確認
まずは、公的保険だけでどこまで保障されるのかを把握しましょう。
高額療養費制度
- 1ヶ月の医療費が一定額を超えると、超過分は払い戻される
- 所得に応じて自己負担限度額が設定されている
傷病手当金
- 病気やケガで働けない場合、給与の約2/3が最長1年半支給
遺族年金
- 亡くなった際、配偶者や子どもに支給される年金
ポイント
公的保障を踏まえて不足分のみ民間保険でカバーすると、重複加入を避けられます。
必要保障額を算出する
- 遺族が必要とする生活費
- 教育費や住宅ローンの残債
- 貯蓄額・公的保障額との差額
→ この不足分だけを民間保険で備える
特約を減らす・シンプルな保険にする
- 先進医療特約や通院特約など、不要な特約を外す
- 医療保険は入院給付金のみのシンプルなプランに変更する
掛け捨て型の保険を活用する
- 貯蓄型(終身保険)は保険料が高い
- 必要保障を掛け捨て型(定期保険)でカバーすると安くなる
保険料の安い会社に乗り換える
- ネット保険(ライフネット生命、楽天生命など)は対面型より安い
- 同じ保障内容でも数千円安くなるケースが多い
支払い方法・契約期間を工夫する
- 年払いにすると月払いより数%安い
- 若いうちに長期契約することで、保険料を固定できる
医療保険をやめる選択肢も
- 高額療養費制度+貯蓄で十分な場合、医療保険は不要なこともある
- がん保険や三大疾病保険など、リスクが高い部分だけに絞る方法も
保険見直しの注意点
解約のタイミング
- 新しい保険が成立してから旧保険を解約する
- 空白期間を作ると保障が途切れるリスクあり
健康状態による加入制限
- 病歴や通院中の場合、新しい保険に入りづらい
- 健康なうちに見直すのがベスト
老後資金とのバランス
- 保険料を下げすぎて老後資金や貯蓄が不足するリスクも
- 必要保障額の計算を慎重に行う
家族構成の変化に応じた見直し
- 結婚・出産・住宅購入などライフステージごとに再チェック
保険相談サービスを活用する方法
- FP(ファイナンシャルプランナー)や保険ショップを利用すると複数社の比較が可能
- オンライン相談も増えており、自宅からでも気軽に相談できる
- ただし、販売手数料目的の提案には注意し、中立性のある相談先を選ぶ
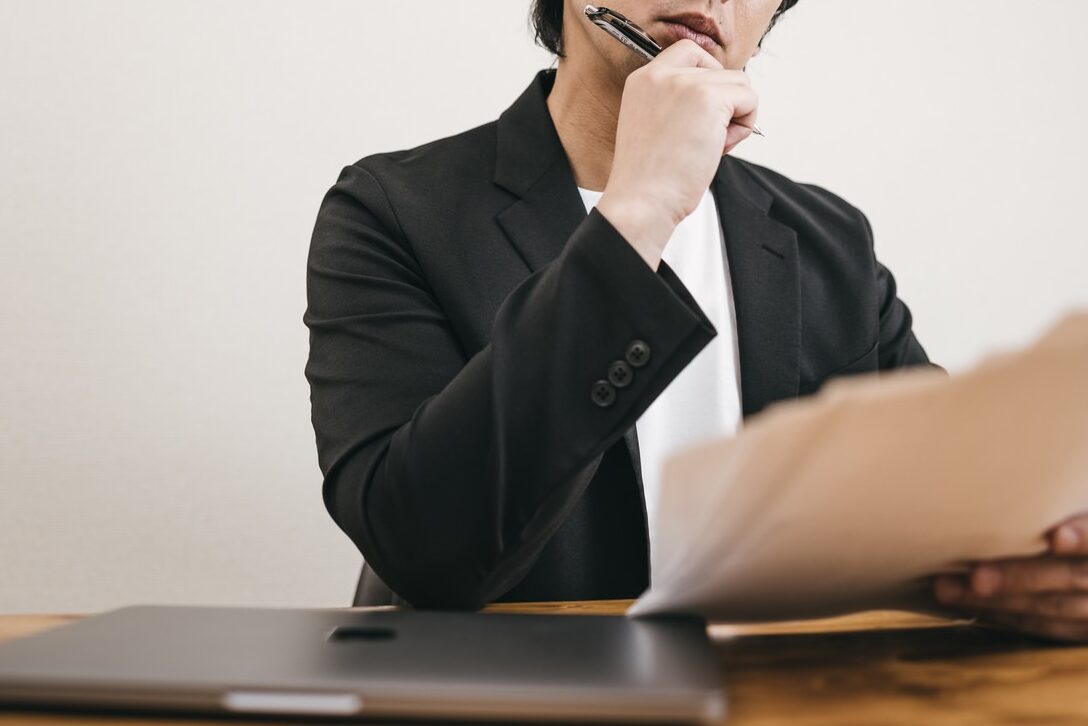
まとめ
民間保険の保険料を抑えるには、まず公的保険で受けられる保障を正しく理解することが重要です。
- 公的保険+貯蓄で不足する部分だけを民間保険で補う
- 不要な特約や重複保障を外し、掛け捨て型やネット保険を検討
- ライフステージの変化に合わせて定期的に見直す
これだけで、月数千円〜1万円以上の節約につながる可能性があります。
固定費を減らして、将来の貯蓄や投資に回せる余裕を作りましょう。
↓関連記事





