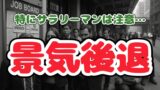靴磨きの少年の逸話とは
投資の世界には「靴磨きの少年の話」という有名なエピソードがあります。
これは1929年の世界大恐慌が起きる直前の出来事です。
街角で靴を磨いていた少年が投資家に株式の話をしたことから、市場の異常な熱狂を示す象徴的な出来事として語り継がれています。
投資を学ぶ人にとって、バブルとその崩壊を理解するための重要な教訓と言えます。

ジョセフ・ケネディと靴磨きの少年
逸話の中心人物はアメリカの投資家ジョセフ・ケネディです。
彼は靴を磨いてもらっている最中、少年から「この株が上がる」「今は投資のチャンスだ」と熱心に話しかけられました。
ケネディはその瞬間に危機を察知しました。
「靴磨きの少年まで株を語るようになったのなら、市場はすでに行き過ぎている」
そう考えたケネディは、自分の保有株をすぐに売却したといわれています。
世界大恐慌と市場の崩壊
その後まもなく、アメリカ市場は大暴落を迎えました。
1929年のニューヨーク株式市場の大暴落は世界中に波及し、世界大恐慌へとつながります。
多くの投資家が莫大な資産を失いましたが、ケネディは早めに撤退したことで損失を免れたのです。
靴磨きの少年の話は、バブルの頂点を示す警鐘として今も語り継がれています。
なぜ靴磨きの少年が象徴的なのか
当時、株式投資は限られた人だけが行うものでした。
そのため、靴磨きの少年のように生活のために働いている人が株式に関心を持ち、具体的な銘柄まで語ることは異常な状況だったのです。
つまり、投資に無縁の層まで熱狂に巻き込まれていたことが、バブル崩壊のサインだったといえます。

群衆心理が生むバブル
市場では群衆心理が大きな影響を与えます。
最初は一部の人だけが参入し、利益を得て口コミが広がります。
やがて「投資すれば誰でも儲かる」という雰囲気が大衆を動かし、次々に新しい参加者が市場に流れ込みます。
その結果、実態とかけ離れた価格上昇が起こり、最後には崩壊するのです。
靴磨きの少年の話は、この群衆心理を象徴する逸話です。
現代に見られる類似の現象
この逸話は過去のものではなく、現代にも同じ構造が繰り返されています。
2000年のITバブルでは、インターネット関連株に大衆が熱狂しました。
2017年や2021年には仮想通貨ブームが起こり、専門知識を持たない層まで投資を始めました。
株式市場でも短期間で急騰した銘柄がメディアで話題になり、誰もが「今がチャンス」と語る光景が見られます。
これはまさに靴磨きの少年の再現といえる状況です。

バブルの兆候を見極めるヒント
投資家が注意すべきバブルの兆候にはいくつかの共通点があります。
・短期間で異常な価格上昇が続く
・普段投資をしない人まで投資の話をしている
・「必ず儲かる」「リスクはない」といった言葉が流行する
・金融商品が社会現象のように話題になっている
これらは過去のバブルに共通するサインです。
投資家に必要な冷静さ
市場が熱狂しているときほど冷静でいることが大切です。
大衆が夢中になっているときに買うことは、バブルの頂点で高値をつかむ可能性が高いのです。
逆に、大衆が恐怖で市場から離れているときにこそ、冷静な投資家は良い投資機会を見つけられます。
靴磨きの少年の話は「群衆に流されないこと」がいかに重要かを教えてくれます。
リスク管理と分散投資
バブルを完全に避けることは難しいですが、リスクを抑えることは可能です。
投資資産を複数の銘柄やセクターに分散する。
長期的な視点を持ち、短期的な熱狂に惑わされない。
そして常に余剰資金で投資を行う。
こうした基本的なルールを守ることで、靴磨きの少年のようなサインを見逃さずに済むのです。

靴磨きの少年の話が示す普遍的な教訓
この話が現代まで語り継がれるのは、時代や商品が変わっても人間の心理は変わらないからです。
株、土地、IT、仮想通貨と対象は変わっても、大衆が熱狂する現象は繰り返されます。
そのたびに「靴磨きの少年の話」が思い出され、投資家に冷静さを求めるでしょう。
ちなみに杉山としては暴騰時も暴落時も買い続けるキープ・バイイングの精神を推しています。
下げのタイミングでその都度、割安になった株や投資信託を買っていけば、長期で見て負けにくいものと考えております。
より良い未来に向けてコツコツと積み上げていきたいものですね。