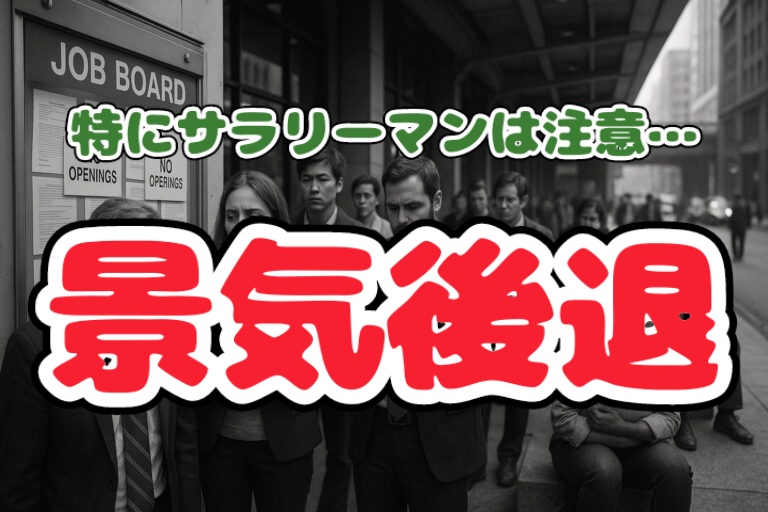景気後退とは、経済活動が全体的に縮小する現象です。
日本語では「不景気」とも言われます。
景気後退になると、企業の売上や利益が減少。
個人の所得も減ることがあります。
失業者が増えることも景気後退の特徴です。
この記事では景気後退の意味、原因、影響、過去の事例をわかりやすく解説します。

景気後退の定義
景気後退は経済全体の活動が停滞する状態です。
一般的には、国内総生産(GDP)が連続して2四半期以上マイナスになると景気後退と判断されます。
GDPは国内で生み出された付加価値の合計を示します。
つまり、モノやサービスの生産・消費が減少することを意味します。
景気後退は自然に起こる場合もあります。
しかし、金融危機や経済ショックによって引き起こされることもあります。
景気後退の原因
消費の減少
人々が将来に不安を感じると支出を控えます。
支出が減ると企業の売上が落ちます。
投資の減少
企業が設備投資や研究開発を控えると経済の成長が鈍ります。
輸出の減少
海外需要が落ちると国内企業の売上が減ってしまいます。
金融政策や財政政策の影響
金利が急上昇したり、税金が増えると経済活動を抑制。
予期せぬ経済ショック
震災やパンデミック、国際紛争などが景気を急減速させます。

景気後退の影響
景気後退は企業や個人の生活に影響します。
企業は売上減少により利益が圧迫されます。
その結果、リストラや賃金カットが行われることがあります。
個人は収入が減る可能性も。
失業(サラリーマンとしてはこれが一番怖いところ…)やボーナス減少、昇給停止などが起こる場合もあります。
消費が減るため、サービス業や小売業も打撃を受けます。
住宅ローンや借金の返済が重く感じられる人も増えるでしょう。
景気後退は経済全体の活力を低下させます。
過去の日本の景気後退事例
日本では過去に複数の景気後退がありました。
・バブル崩壊
土地や株の価格が急落し、企業や銀行が大きな損失を出しました。
1990年代は「失われた10年」と呼ばれ、長期の景気低迷が続きました。
住宅市場や株式市場も停滞し、雇用環境も厳しくなりました。
・リーマンショック
アメリカ発の金融危機が世界に波及し、日本経済も輸出減と株安で打撃を受けました。
失業率が上がり、消費や投資も冷え込みました。
・新型コロナウイルス感染症
緊急事態宣言により消費やサービス業が大きく落ち込みました。
政府や中央銀行の対応で回復は早かったものの、一時的に経済活動は大幅に縮小しました。

景気後退と株式市場
景気後退は株式市場にも影響します。
企業業績の悪化が株価に反映されます。
多くの株価指数が下落。
個別株の業績や配当も不安定になりやすいです。
しかし、景気後退期でも優良企業の株は比較的安定する場合があります。
投資家は景気動向に注目しながら、長期目線で判断することが大切です。
景気後退時の対策
個人は支出を見直すことが重要です。
貯蓄を増やし、生活費の見直しを行いましょう。
リスク資産の保有は慎重に。
分散投資で損失リスクを減らすことも有効です。
企業はコスト管理や事業効率化が求められます。
新規投資は慎重に判断する必要があります。
政府や中央銀行は、金融緩和や景気刺激策で景気後退を緩和。
公共事業や減税、低金利政策などが典型例です。

景気後退を理解するメリット
景気後退を理解すると経済ニュースや投資判断がわかりやすくなります。
景気後退の兆候を知ることで、生活や資産運用の対策を取れます。
過去の事例から学ぶことで、ある程度リスクに備えることができるでしょう。
長期的な資産形成や貯蓄戦略にも役立ちます。
まとめ
景気後退とは、経済活動が全体的に縮小する現象です。
GDPが連続して減少することで判断されます。
原因は消費や投資の減少、輸出低迷、金融政策、経済ショックなど。
影響は企業業績の悪化、失業率上昇、個人の生活圧迫など多岐にわたります。
過去のバブル崩壊、リーマンショック、コロナ禍が代表例です。
株式市場や投資にも影響を与えます。
個人や企業はコスト管理や資産分散などで備えることが重要です。
転ばぬ先の杖です!普段から意識していきましょう。
より良い未来のために、です。