はじめに
ここ数年、日本でも「インフレ(物価上昇)」が身近なものになってきました。スーパーでの食料品、ガソリン、電気代、さらには外食の値段まで、気がつけばじわじわと上がっています。
2025年現在、日本の消費者物価指数(CPI)は3%前後の上昇が続いており、日銀の目標2%を上回る状況が定着しています。
「たった3%くらいなら大したことないのでは?」と思う人も多いでしょう。ですが、インフレの怖さは複利的に効いてくるところにあります。1年だけでなく10年、20年と続いた場合、お金の価値は大きく削られてしまうのです。
この記事では、インフレが続いた場合に私たちの資産がどのように減っていくのかを「複利」や「72の法則」を用いてわかりやすく解説します。そして、インフレ時代にどう資産を守り、増やすべきかについても考えていきましょう。

インフレとは何か?改めておさらい
インフレとは、モノやサービスの価格が全体的に上昇する現象を指します。裏を返せばお金の価値が下がることを意味します。
例えば去年100円で買えたおにぎりが、今年は110円になっていたとします。このとき、モノの値段が上がったのと同時に、100円というお金の購買力が小さくなったとも言えるのです。
- 100円で買える量が減る
- 生活コストが増える
- 現金の価値が目減りする
このように、インフレは「知らない間に資産を奪っていく」性質を持っています。特に給与が上がらない場合は、実質的な生活水準が下がってしまうのです。
インフレが複利で効いてくる理由
多くの人は「物価が毎年3%上がる」と聞くと、単純に「10年で30%上がる」と考えがちです。しかし、実際にはそう単純ではありません。インフレは複利的に効いてくるのです。
たとえば、毎年3%のインフレが続いた場合、10年後の物価水準はどうなるでしょうか?
計算式
未来の物価水準 = 現在の物価 × (1 + インフレ率)^年数
100円の商品が毎年3%ずつ値上がりするとすると:
- 10年後:100円 × (1.03)^10 ≒ 134円
- 20年後:100円 × (1.03)^20 ≒ 181円
- 30年後:100円 × (1.03)^30 ≒ 243円
つまり、30年後には同じ100円の商品を買うのに243円必要になるのです。
これは「利息が複利で増える」のと同じ原理で、インフレもまた「複利でお金の価値を削っていく」ことを意味します。

72の法則でインフレの影響を直感的に理解する
ここで役立つのが「72の法則」です。これは、資産が何年で2倍になるかを簡単に計算できる近似式で、投資の世界ではよく使われます。
計算式はとてもシンプルです:
72 ÷ 年率(%) ≒ 2倍になる年数
これをインフレに当てはめるとどうなるでしょうか?
- インフレ率2% → 72 ÷ 2 = 36年で物価が2倍
- インフレ率3% → 72 ÷ 3 = 24年で物価が2倍
- インフレ率5% → 72 ÷ 5 = 14.4年で物価が2倍
つまり、現在の日本のように3%前後のインフレが続けば、24年後には生活コストが2倍になるという計算になります。これはかなりのインパクトです。
仮に現在の生活費が月15万円だとしたら:
- 24年後には月30万円必要
- 年間生活費は180万円 → 360万円に
もし給料や年金がそれほど増えなければ、老後の生活は一気に苦しくなってしまいます。
インフレが家計に与える影響
インフレが長期的に続くと、具体的にどんな影響があるのでしょうか?
食費
毎年3%上がると、10年後には34%増し。
毎月5万円の食費が、10年後には約6万7千円に。
住宅ローン・家賃
ローンは金利次第ですが、家賃はインフレに連動して上がることが多いです。
10万円の家賃が、20年後には18万円近くになる可能性も。
老後資金
現在の水準で「老後は2000万円必要」と言われていますが、インフレを加味すると金額は大きく変わります。
3%インフレが20年続けば、実際には約3600万円必要になります。
このように、インフレを軽視すると「将来必要なお金」を大幅に見誤ってしまうのです。

インフレ時代に現金貯金が危険な理由
「銀行にお金を預けておけば安心」と考える人は多いですが、インフレ時代には逆に危険です。
- 銀行の普通預金金利 → 0.001%程度
- インフレ率 → 3%
つまり、預金しているだけで毎年「実質3%ずつ資産が目減りしている」ことになるのです。
1000万円を銀行に寝かせていたら、10年後には実質的に740万円程度の購買力しかなくなります。これこそ「サイレントな資産の強奪」とも言える現象です。
インフレに強い資産とは?
では、どうやって資産を守ればよいのでしょうか?インフレに強いとされる資産の代表例を挙げます。
- 株式:企業の利益は物価にある程度連動するため、長期的にはインフレヘッジになる
- 不動産:賃料や土地の価格はインフレに強い傾向がある
- コモディティ(原油・金など):インフレが高まると価格が上昇しやすい
- インフレ連動国債:物価に応じて利払いが増える仕組み
もちろんリスクはありますが、現金一本に頼らないことが重要です。
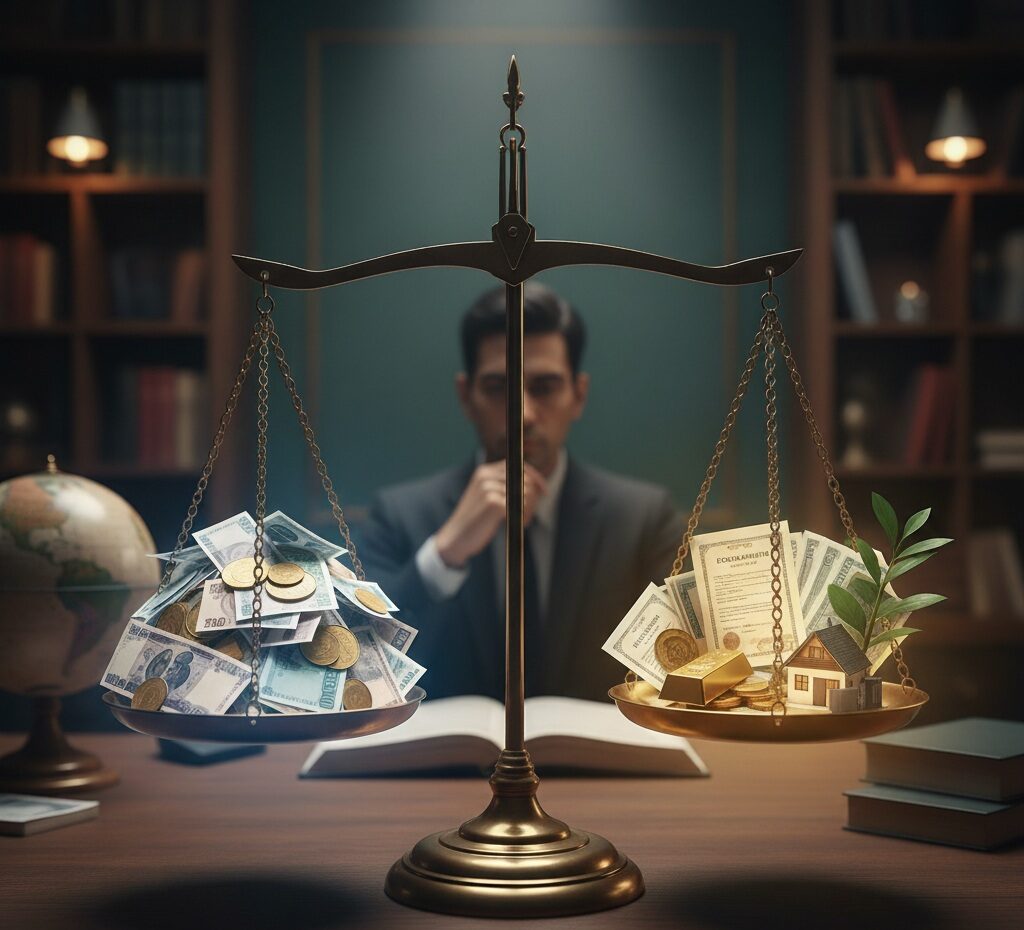
複利は敵にも味方にもなる
ここまで見てきたように、インフレは複利的に効いてくるため放置すれば資産が削られていきます。ですが、逆に「投資」も複利で効いてきます。
例えば、年利5%で運用できれば:
- 10年後:資産は約1.6倍
- 20年後:約2.7倍
- 30年後:約4.3倍
インフレ率3%より高い利回りを出せれば、実質的に資産を増やし続けることができます。つまり複利は「敵(インフレ)」にも「味方(投資)」にもなるのです。
まとめ:インフレ時代に生き残るために
インフレ率3%が続けば、24年で物価は2倍になります。これは複利と72の法則で簡単に理解できます。
- インフレはお金の価値をじわじわ奪う
- 銀行預金だけでは資産を守れない
- 投資を通じてインフレ率を上回るリターンを得ることが重要
- 複利を味方につければ、資産は守れるだけでなく増やせる
将来の生活を守るためには、「現金の価値は減る」という前提に立ち、資産運用を取り入れることが避けられません。固定観念を捨て、インフレと複利の力を理解することが、将来のこころの安定に繋がることでしょう。







