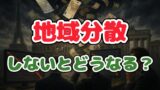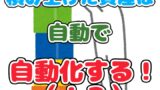株価が高値圏にあるときに投資をためらう心理「高所恐怖症」とは
ニュースで「日経平均が過去最高値を更新」と聞くと、「今から投資しても遅いのでは?」と感じる人も多いかと思います。
この心理的なブレーキは、投資の世界で「高所恐怖症」と呼ばれます。
株価が高い水準にあると、今後の下落リスクを過大に見積もってしまい、本来のチャンスを逃すことがあります。
しかし冷静に考えると、相場が高値を更新するのは「企業価値が上がっている」証拠でもあります。
いつも通り短期的な値動きに振り回されず、長期の視点で見ることが重要です。

株価が高い時に投資をためらう心理的な理由
多くの投資初心者は、「高く買って安く売る」ことを避けたいという心理が働きます。
過去の暴落の記憶や「今はバブルだ」という報道も、この恐怖心を強めます。
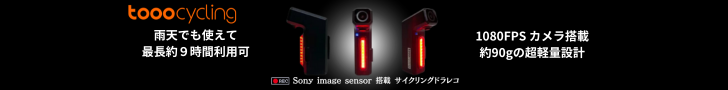
また、株価チャートの右肩上がりを見て「もう天井だろう」と思い込むこともあります。
このように、人間の感情は投資判断を誤らせる最大の要因です。
大切なのは、感情ではなく「データ」と「戦略」に基づいて投資を行うことです。
高値圏でも投資を続ける人の特徴
株価が高くても淡々と投資を続ける人には、いくつかの共通点があります。
それは、「長期的な視点を持ち、相場の一時的な上下に動じない」ことです。
また、毎月決まった金額を自動で積み立てる「ドルコスト平均法」を実践しているケースが多い印象ですね。
市場が上がっても下がっても買い続けることで平均購入単価が平準化され、リスクを分散できます。
こうした人たちは相場の短期的な騰落ではなく、時間を味方につけています。

ドルコスト平均法で高値の恐怖を和らげる
ドルコスト平均法とは、一定の金額を定期的に投資し購入単価を平均化する方法です。
この手法を使えば「いつ買うのがベストか」を考えずに済みます。
たとえば毎月5万円を投資信託に積み立てる場合、株価が高いときは少なく、安いときは多く購入することになります。
その結果、長期的に見て平均購入価格が安定し、暴落の影響を受けにくくなります。

人類の歴史は長期で見れば右肩上がりなので、平均を狙うのがかなり有効な手段であることは間違いありません。
分散投資でリスクをコントロールする
株価が高値を更新しているときは、「すべての資金を一度に投資する」ことを避けるのが賢明です。
一つの銘柄や一つの国だけに集中すると、下落時のダメージが大きくなります。
そこで有効なのが「分散投資」です。
日本株、米国株、新興国株、債券、リートなど、複数の資産に分けて投資することで、相場変動の影響を和らげられます。
リスクをコントロールしながら資産を増やすためには、分散投資は欠かせません。
投資の「タイミング」を完璧に読むのは不可能
多くの人が「もっと下がったら買おう」と考えますが、実際には底値を見極めるのは非常に困難です。
市場のタイミングを完璧に当てることができる人は存在しないと言ってもいいでしょう。

過去のデータを見ても「安いときに買って高いときに売る人」より、長期間投資を続けた人のほうが高いリターンを得ています。
相場の上下を気にするよりも「市場に居続けること」のほうが重要です。

高値圏での投資は「少額・継続」が基本
株価が高いときに一括で大金を投資するのはリスクがあります。
そのため、高値圏では「少額で継続的に投資する」ことが重要です。
例えば毎月の給料の一部を自動で積み立てる形にすれば、相場の上下に一喜一憂せず続けられます。
この仕組み化が、感情に流されない投資を支える最大の武器となります。
投資を日常の習慣にしてしまうことが、長期成功への近道です。
長期なのに近道とはこれいかに…でも歴史を見ると積み立て投資は強いんですね。
高値恐怖症を克服するための心構え
「投資は怖い」と感じるのは自然なこと。
ですが、その恐怖に負けて何もしないと、せっかくの資産形成のチャンスを逃してしまいます。
重要なのは「リスクを理解し、受け入れたうえで行動する」ことです。
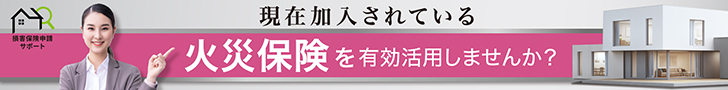
市場は常に上下しますが、長期的に見れば経済は成長を続けています。
自分のリスク許容度を知り、ブレないルールを持つようにしましょう。

まとめ:恐怖に勝ち、継続する人が最終的に勝つ
高値恐怖症は誰にでも起こる自然な感情です。
しかしその感情に支配されると、せっかくの投資チャンスを逃してしまいます。
長期投資の世界では「いつ始めるか」よりも「いつまで続けるか」が重要。
ドルコスト平均法や分散投資を活用し、相場の波を乗り越えながら資産を増やしていきましょう。
恐れず一歩を踏み出した人だけが、将来の経済的自由を手に入れることができます。
皆で一歩ずつ歩みを進めていきましょう!